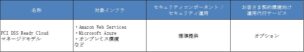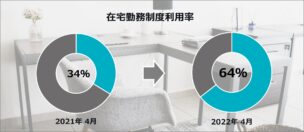明日のハイブリッド量子コンピューターの構築に着手する時が来ました。
差し迫った動機があり、進むべき道は明確であり、ジョブの主要コンポーネントは現在すでに提供されています。
量子コンピューティング( https://blogs.nvidia.co.jp/2021/04/16/what-is-quantum-computing/ )は、今日の最も困難な課題のいくつかを打ち破る可能性を秘めており、創薬から天気予報まですべてを前進させます。つまり、量子コンピューティングは HPC の将来に大きく貢献するでしょう。
今日の量子シミュレーション
量子シミュレーションの未来を作るのは簡単なことではありませんが、作るためのツールはすでに存在しています。
その第一歩として、今日のスーパーコンピューターは、比較的小さくエラーが発生しやすい今日の量子システムの能力を超える規模とパフォーマンス レベルで、量子コンピューティングのジョブをシミュレートできるようになっています。
量子技術を扱う数十の組織がすでに NVIDIA cuQuantum ( https://developer.nvidia.com/cuquantum-sdk )ソフトウェア開発キットを使用して GPU 上で量子回路シミュレーションを高速化しています。
AWS はこのほど、Braket サービスで cuQuantum ( https://aws.amazon.com/blogs/quantum-computing/accelerate-your-simulations-of-hybrid-quantum-algorithms-on-amazon-braket-with-nvidia-cuquantum-and-pennylane/ )が利用可能になったことを発表しました。同社はまた、cuQuantum が量子機械学習ワークロードで最大 900 倍の高速化を提供する方法を Braket 上で実証( https://aws.amazon.com/blogs/quantum-computing/using-embedded-simulators-in-amazon-braket-hybrid-jobs/ )しました。
cuQuantum はまた、Google の qsim、IBM の Qiskit Aer、Xanadu の PennyLane、Classiq の Quantum Algorithm Design プラットフォームなど大手の量子ソフトウェア フレームワークでのアクセラレーテッド コンピューティングを実現しています。これらのフレームワークのユーザーは、追加のコーディングなしで GPU アクセラレーションにアクセスできるのです。
そして、新たにMenten AI が、同社の量子機能に対応できるよう、cuQuantum を利用する企業の一員となりました。
サンフランシスコ ベイエリア発の創薬系スタートアップである Menten AI は、cuQuantum のテンソル ネットワーク ライブラリを使用して、タンパク質の相互作用のシミュレーションや新しい薬物分子の最適化に取り組む予定です。量子コンピューティングの可能性を利用してドラッグ デザインを高速化することを目指しています。ドラッグ デザインの分野は化学自体と同じく、量子アクセラレーションの恩恵をいち早く受ける分野の 1 つと考えられています。
具体的には、Menten AI は治療法の設計において多くの演算を必要とする問題を解決すべく、量子機械学習を含む一連の量子コンピューティング アルゴリズムを開発中です。
「これらのアルゴリズムを実行できる量子コンピューティング ハードウェアの機能はまだ開発段階にありますが、NVIDIA cuQuantum のような古典的なコンピューティング ツールは、量子アルゴリズムの開発を進める上で欠かせません」と、Menten AI の主任サイエンティストであるアレクセイ ガルダ (Alexey Galda) 氏は言います。
量子リンクの構築
量子システムが進化する中、次の大きな飛躍はハイブリッド システム、つまり、量子コンピューターと古典コンピューターが連動するシステムへの移行です。研究者たちは、新しくパワフルなクラスのアクセラレータとして機能するシステム レベルの量子プロセッサ (QPU) のビジョンを共有しています。
そこで、目下の最大の任務の 1 つとなるのが、古典システムと量子システムをハイブリッド量子コンピューターに橋渡しすることです。これを成し遂げるには 2 つの大きな要素が必要となります。
第一に、GPU と QPU の間に高速かつ低遅延の接続が必要となります。この接続により、ハイブリッド システムは、回路の最適化、キャリブレーション、エラー訂正といった古典的なジョブに、卓越した GPU を使用できるようになります。
GPU はこれらのステップの実行時間を短縮し、今日のハイブリッド量子ジョブにおける主なボトルネックとなっている、古典コンピューターと量子コンピューター間の通信のレイテンシを軽減できます。
第二に、業界は効率的で使いやすいツールを備えた統合プログラミング モデルを必要としています。HPC と AI におけるNVIDIA の経験により、NVIDIA だけでなくユーザーも、強固なソフトウェア スタックの価値を認識しています。
ジョブに適したツール
今日の QPU をプログラムするにあたり、研究者たちは低レベルのアセンブリ コードと同レベルの量子を使用せざるを得ない状況にありますが、これは量子コンピューティングを専門としていない科学者の範疇を超えるものです。また、開発者には統合プログラミング モデルとコンパイラ ツールチェーンがありません。これがあれば開発者たちは任意の QPU で作業を実行できるようになります。
この状況は変わる必要があり、まもなく変わります。3 月のブログ( https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/hybrid-quantum-computing-ecosystem/ )で、プログラミング モデルの改善に向けて動き出したばかりの取り組みについて、いくつか説明しています。
量子コンピューターが作業を加速できる方法を効率的に見つけるために、科学者たちは HPC アプリの一部を、まずはシミュレートされた QPU に、その後は実際の QPU に、容易に移植できなければなりません。そのためには、高性能かつ使い慣れた方法で HPC アプリを動作できるようにするコンパイラが必要です。
GPU で高速化されたシミュレーション ツールとプログラミング モデル、およびコンパイラ ツールチェーンを組み合わせてすべてを 1 つにまとめることで、HPC 研究者たちは、明日のハイブリッド量子データセンターの構築に着手できるようになります。
今から始めるには
量子コンピューティングは、数十年先のSF (サイエンス フィクション) のように聞こえる人もいるかもしれません。しかし実際、研究者たちが構築する量子システムは毎年規模が大きくなっています。NVIDIA はこの取り組みに尽力しており、より多くの人たちと共に明日のハイブリッド量子システムを構築したいと思っています。
詳細を知りたい方は、GTC セッション( https://www.nvidia.com/ja-jp/on-demand/session/gtcspring22-s42065/?playlistId=playList-e06afe6b-d8f9-4c57-9fdf- )をご覧の上、このトピックを扱う ISC のチュートリアル( https://app.swapcard.com/widget/event/isc-high-performance-2022/planning/UGxhbm5pbmdfODYxMTM5 )をぜひご覧ください。今GPU でできることについて詳しく知りたい方は、NVIDIAのState Vector( https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-quantum-circuit-simulation-with-nvidia-custatevec/ )やTensor Network( https://developer.nvidia.com/blog/scaling-quantum-circuit-simulation-with-cutensornet/ )ライブラリについての記事をお読みください。
 ファーウェイデータセンター施設チームCTOの費珍福(フェイ・ジェンフー)
ファーウェイデータセンター施設チームCTOの費珍福(フェイ・ジェンフー)